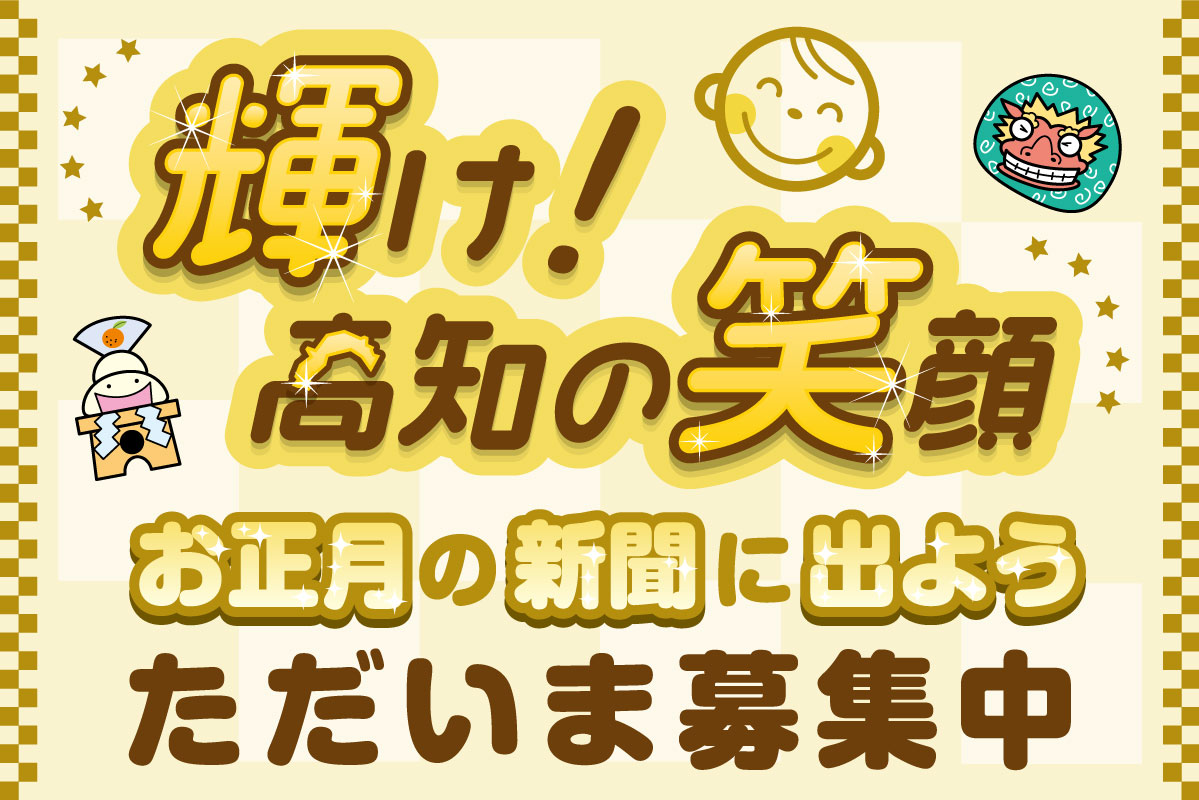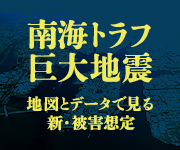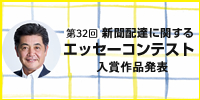2025.09.12 08:35
【全文公開中】寝耳に水 反対通らず―文化で稼ぎますか?高知県施設公募方針を考える(1)

2025年度末で指定管理期間が終わる高知城歴史博物館と公募方針を記した県資料(コラージュ=松本康裕作成)
「公社等外郭団体のあり方見直しについて」。財団が運営する美術館と坂本龍馬記念館を含め、県立5施設の指定管理者を県の直指定から公募に切り替える方針が記されていた。
「自律的に事業を実施し収益を上げていくことで団体職員の処遇改善、人材確保などの効果が期待できる」。そんな狙いとともに「代行料の精算を免除する」とも書かれていた。
直指定の団体は、県からの管理代行料と利用料収入から、支出を引いた剰余金を県に納める必要がある。それを免除するとは、収益は全て団体のものになるということ。ただ、公募で選ばれれば、だ。
用紙には、公募の要項や管理代行料の先行きの記述はない。鎌倉理事長の頭に疑念、懸念が渦巻く。「文化施設で稼げと?」「稼げないと職員の処遇は下がるのか?」「公募なら職員は雇用に不安を抱く」
県OBでもある鎌倉理事長は率直に伝えた。「すまんが、大反対やぞ」
■ ■
公募対象は他に牧野植物園、高知城歴史博物館、のいち動物公園。県牧野記念財団、土佐山内記念財団、県のいち動物公園協会が運営し、文化財団を含めていずれも県の外郭団体だ。
県はこれらの団体を「自律性向上団体」と位置付ける。剰余金の返納免除のほか、職員給与への関与もやめ、常勤役員は公募するよう要請する―という。
公募方針は6月、県議会総務委員会で議員に説明された。鎌倉理事長の反対は受け流され、予想通り、各施設を懸念と反発が覆う。
「雇用が不安定になれば優秀な人材が流出する」「稼ぐことに傾けば地道な調査研究が阻害される」。本紙は8月1日付で施設職員の声とともに県の公募方針を報じた。
県が同9日まで約1カ月間行ったパブリックコメントには301の個人・団体から794件の意見が寄せられた。異例の多さで、大半は雇用不安や専門性の低下などの危惧だという。
■ ■
県は9月、運営団体に再度、説明して回っている。
「公募で仮に事業者が変わっても、専門性や継続性を担保する観点から、希望する職員は現状を下回らない処遇で継続雇用されるよう公募要領に配慮する」
「運営に必要な財源はこれまで通り、指定管理代行料として支払う」
現場の反発は消えていない。ある施設職員は県の姿勢に「後出しじゃんけん」と顔をしかめる。関係者にとっては、公募方針こそが「寝耳に水」。施設との意見交換もなく、唐突に下ろされた憤りは強い。
今回の公募方針は、文化施設の担当課ではなく、県庁組織の運営管理や行財政改革を担う行政管理課が主導する。県の清水敦・総務部長は「今が政策決定の過程だ」と強調するが、ちぐはぐな対応もあった。
パブコメ終了後の9月10日、城博館の資料の保存・管理に限っては、公募の対象外とする方針変更が明らかになった。山内家が寄贈・寄託した宝物を保存・管理するために土佐山内記念財団ができた経緯を、県が軽んじていた事情が浮かぶ。
城博館の直指定は2025年度末で終わり、5施設で最も早い。次の管理者の公募を始める時期は県の「標準スケジュール」では8月ごろ。もう過ぎている。
それでも県は公募にこだわる。「なぜ、そんなに急ぐのか」といぶかる声は県庁内でも聞こえる。発端を探ると、一昨年に起きたある問題に行き当たった。
◆
本県の文化芸術、科学研究が「収益」で揺さぶられている。波紋を広げた公募方針の背景と論点を探り、文化行政の行方を問う。 (報道部・谷川剛章)
【ズーム】指定管理者の直指定
指定管理者の直指定 自治体が、公共施設の運営を任せる指定管理者を選ぶ手法の一つ。民間業者などの公募はせず、管理者を直接指定する。専門性などの観点から文化施設に限ることが多い。高知県は2004年度に指定管理を始め、06年度から一部施設で直指定を導入。今年4月現在、指定管理41施設のうち10施設を直指定している。
【連載一覧】
(2)端緒は牧野植物園 離職相次ぐ
(3)「金にならない」役割負う
(4)研究成果 県民還元は…
(5)「公募 周回遅れで古い」
(6)公募で施設に「緊張感」
(7=終)見えぬ未来像 まず対話を