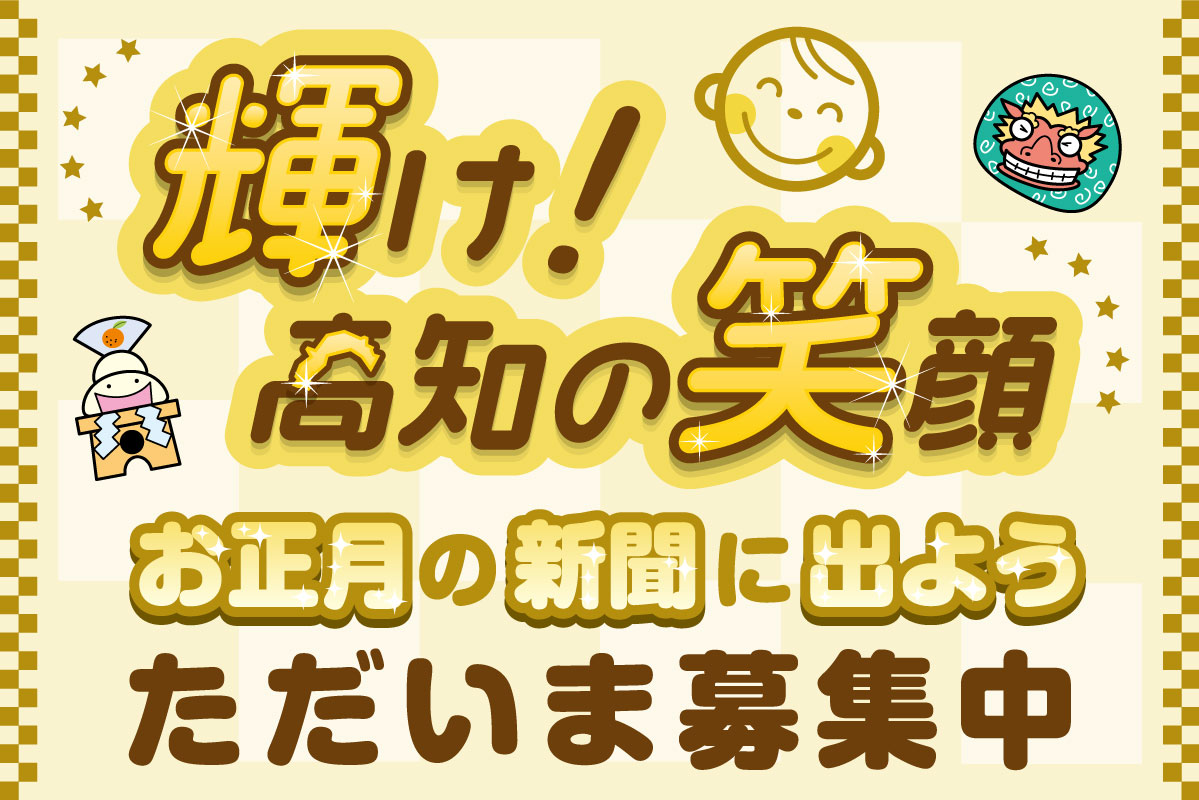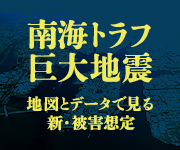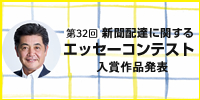2025.11.05 05:00
【再審制度見直し】改悪しては意味がない

見直しを検討する法制審議会(法相の諮問機関)の部会で、再審開始を左右する証拠開示の法規定化について法務省が2案を示した。開示の対象範囲を再審請求理由に関連する証拠に限るA案と、一定の類型に当てはまる証拠も含めるB案だ。
部会では、弁護士以外の法曹関係者らからA案を推す意見が相次いだという。だが、本当にA案でよいのか疑問がある。
刑事訴訟法は、再審の開始には無罪などを言い渡すべき明らかな新証拠が必要とする。ところが、事件に関する証拠は裁判に提出されなかったものも含め警察や検察が収集し、保管している場合が多い。
再審請求審でそれらがいかに開示されるかが再審開始の鍵になるが、現行の刑訴法には具体的な規定がない。そのため、裁判所が請求審において職権で開示の必要性や範囲を決めてきた。
つまり裁判官の意識次第の面がある。それを法で規定する意義は大きいが、A案では裁判官の裁量より開示範囲が狭くなる恐れがある。
過去、再審を通じて、検察側が元の裁判で被告の無罪につながる重要な証拠を提出していなかった例が多く判明している。その点でも範囲は重要であるはずだ。
刑事裁判は地裁、高裁、最高裁の三審制を敷く。部会論議では再審請求審で幅広い証拠が開示されれば、事実上の「4審化が懸念される」との声が出た。
通常裁判の重みが薄れるとの懸念のようだが、昨年も元死刑囚、袴田巌さんの再審無罪が確定したように冤罪は一向になくならない。まさに刑事司法の信頼が問われている。
滋賀県の病院で看護助手が入院患者を殺害したとして有罪判決を受け、服役後の2020年に再審無罪が確定した事件では、再審を担当した大津地裁の裁判長が判決後、説諭でこう述べている。「取り調べや客観証拠の検討、証拠開示のどれか一つでも適切に行われていれば、このようなことにならなかった」
適正な捜査、立件、裁判が行われることが第一だが、もしもの場合、再審制度は冤罪被害者を救済する最後の手段となる。それにふさわしい制度でなければならない。
再審開始に検察が不服申し立てを繰り返す問題も長年指摘されている。袴田さんの場合も再審開始までに第1次請求で約27年、第2次請求でも約15年を要した。
政府は来年の刑訴法改正を視野に入れる。改悪にならないよう論議を尽くしてほしい。一方で政府とは別に、野党6党がこうした問題の解消を目指した刑訴法改正案を国会に提出済みだが、審議入りのめどは立っていない。
再審制度の課題を長年放置してきた責任は政府にも国会にもある。いまこそ真摯(しんし)に向き合うべきである。