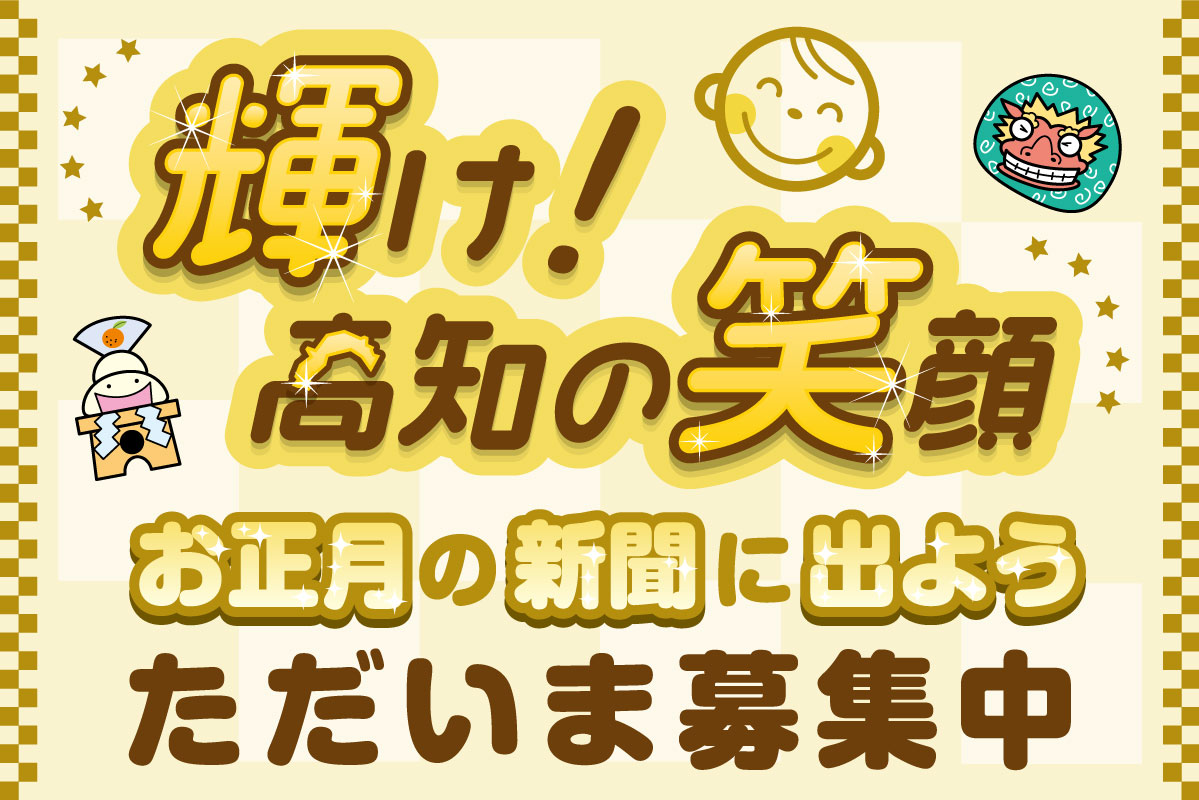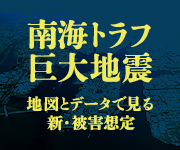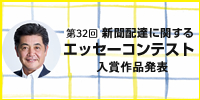2025.09.20 05:00
【日米金融政策】圧力排し独立した判断を

米連邦準備制度理事会(FRB)は主要政策金利を0・25%引き下げることを決めた。利下げは9カ月ぶりで、第2次トランプ政権では初めてとなる。
利下げ再開に踏み切ったのは、雇用減速への対応を優先したためだ。直近の雇用情勢は、需要低迷や不確実性のため企業が採用に慎重となり、解雇や自然減による人員削減が伝えられる。消費支出は横ばいか減少傾向にある。多くの世帯で物価上昇に賃上げが追いついていないことが要因とされる。
雇用悪化への警戒で、昨年9月に4年半ぶりに利下げに転じている。だが、トランプ政権の発足後は関税政策が物価に及ぼす影響を見極めるため、据え置きを続けてきた。
パウエル議長は、関税強化によるインフレへの影響は想定より「緩やかで小さい」と説明した。とはいえ、高関税措置に伴う価格上昇がみられ、インフレ懸念は依然くすぶっている。年内の追加利下げを見込むが、インフレが加速すれば利下げペースに影響する可能性がある。
トランプ大統領はFRBに大幅な利下げを求めてきた。政権の主要政策である減税は財政悪化が見込まれ、国債の利払い費の抑制を狙う。引き下げに慎重なパウエル氏にいらだち、批判を繰り返している。
威圧はFRB理事1人の解任の動きにも発展した。理事会メンバーに意中の人物を据え、利下げ派の過半数獲得を画策する。さらに、雇用統計が下方修正されると改ざんを主張して労働統計局長を解雇するなど、利下げへの統制を強めている。
こうした行為は、中央銀行の独立性や統計の信頼性をゆがめると強い批判が向けられる。FRB歴代2議長は、米経済に悪影響を及ぼすと警鐘を鳴らした。
トランプ氏の指名を受けて就任したミラン新理事は0・5%の引き下げを主張したが、支持は広がらなかったという。政治圧力はひとまずかわした格好だが、どう向き合うかは引き続き課題だ。
米国市場は今回のFRB決定を好感し、主要株価指数の一角が過去最高値を付けた。流れを引き継ぎ、東京株式市場は日経平均株価が連日で取引時間中の最高値を更新した。
一方、日銀は政策金利を現行0・5%程度で維持することを決めた。また、金融緩和のために買い入れた上場投資信託(ETF)を売却し、金融正常化を加速する。
日銀は物価上昇を受けて利上げを模索するが、慎重論も漂う。政治情勢から財政悪化を警戒する市場では、国債が売られて長期金利は上昇している。利上げで景気後退を危惧する見方も強まる。
米関税政策や利下げの影響などを見定めた独自の判断が求められる。ETF売却への市場反応が示すように、対話の重要性が増している。