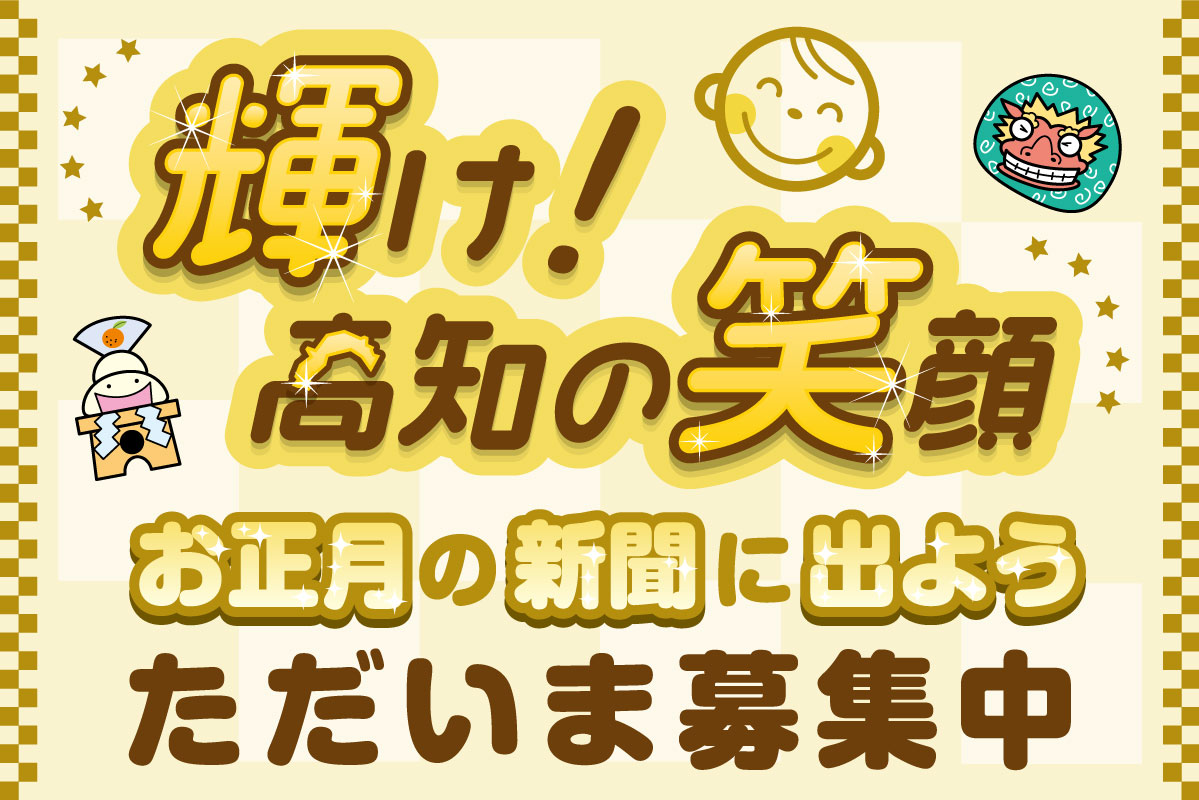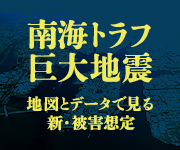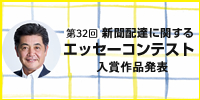2025.04.02 05:00
【南海トラフ地震】命守る取り組みを着実に

政府は前回2012年の想定を基に死者数を8割減らす目標を掲げていたが、全国では1割弱の減少にとどまった。各地で防災対策が進んだにもかかわらず、本県もまた3千人の減少だった。地形データの見直しで浸水地域が拡大したことが大きく影響する。
あくまで最悪のケースで、落胆や厳しい声もあるが目を背けず、「正しく恐れる」意識を持ち続けることが重要になる。官民には従来の対策の継続と強化が求められる。
新想定では、前回と同じく南海トラフ沿いでマグニチュード(M)9クラスの地震が発生したと仮定。震源域や季節、時間帯など複数のパターンで試算した。
県内で死者数が最大になるのは、四国沖を震源とする地震が冬の深夜に発生し、発災後すぐに避難する早期避難率が20%の場合。津波による死者が3万6千人で、死因の8割近くを占める。
一方、同じ条件で早期避難率が70%に上がり、避難の呼びかけが効果的に行われれば、津波の死者は1万3千人に減る。避難率100%では8700人まで減少する。
ハード面の整備だけでは被害を減らせない。迅速な避難が生き延びる可能性を高める。
ただ本県の県民意識調査によると、早期避難意識は7割前後で推移している。一層の意識向上が今後の課題となる。
負傷者は前回の倍近い最大9万9千人と算出された。職場や学校などに人が集まる夏の昼間の想定で、ほとんどが建物倒壊による。耐震化率の向上が欠かせない。
新たな懸念もある。本県に限らず全国各地で、前回から12年余りの間に人口減や高齢化が進み、地域の防災力が弱まっていることだ。
報告書は、このままでは「より厳しい状況に陥る可能性がある」と指摘。行政による対応には限界があるとし、「あらゆる主体が総力を結集して防災対策に臨むことが重要だ」とした。
県は、新想定を前提にした県版被害想定を25年度内にまとめる。地域ごとの課題を洗い出し、実情をより精密に反映させる。県版を基に実効性のある対策を練ってもらいたい。
新想定では、避難生活に伴う体調悪化などで生じる「災害関連死」を初めて試算した。全国で2万6千~5万2千人とされる。
熊本地震や能登半島地震では、直接死よりも関連死が多かった。阪神大震災以降、予防が課題となってきたが、対策は遅い。
政府は昨年12月に避難所の運営指針を改定。1人当たりの面積やトイレの数の改善に向け、国際基準を反映させるよう自治体に促している。国や自治体はこれまでの教訓を踏まえ、避難所生活の質向上に早急に取り組む必要がある。